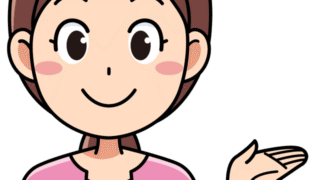 スクールカウンセリング
スクールカウンセリング 案内役が不在の話
ある学校に呼ばれてコンサルテーションをしたときの話です。出迎えてくれた案内役の先生は、私をおいてスタスタと校舎の中に入って戻ってしまいました。慌てて後を追ったときの話です。
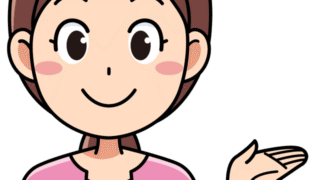 スクールカウンセリング
スクールカウンセリング 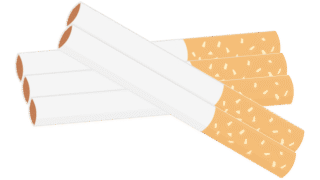 カウンセリング
カウンセリング 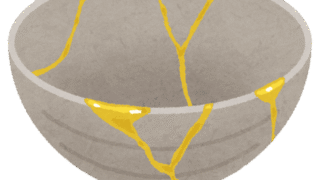 学ぶということ
学ぶということ  生活と心
生活と心  学ぶということ
学ぶということ 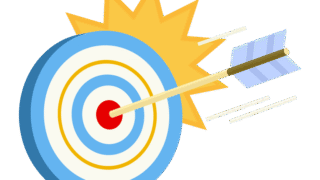 カウンセリング
カウンセリング 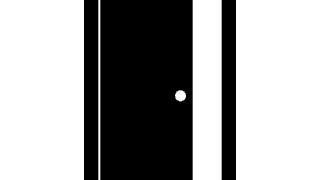 スクールカウンセリング
スクールカウンセリング  スクールカウンセリング
スクールカウンセリング 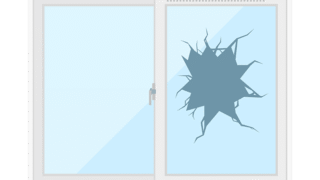 こころの成長
こころの成長  カウンセリング
カウンセリング