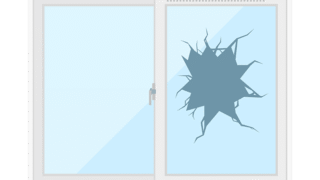 こころの成長
こころの成長 教育的な仮説的ストーリー
スクールカウンセラーは学校の先生たちに、子どもの行動に対する仮説を提案することがあります。その仮説はできるだけ教育的な仮説的ストーリーになるようにしたいと考えています。
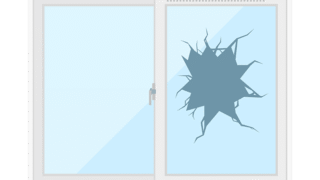 こころの成長
こころの成長  こころの成長
こころの成長  こころの成長
こころの成長  こころの成長
こころの成長  こころの成長
こころの成長 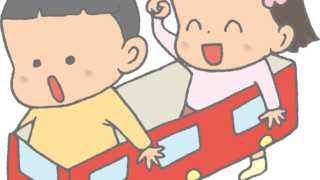 こころの成長
こころの成長  こころの成長
こころの成長  こころの成長
こころの成長  こころの成長
こころの成長  こころの成長
こころの成長