 学ぶということ
学ぶということ まずAIに聞いてみる
カウンセリングに来る前に、自分のことをAIに相談している人が増えてきています。ですからカウンセラーの方もそのことを前提にしておいた方が良いと思います。最近の学校臨床とAI事情を考えてみました。
 学ぶということ
学ぶということ 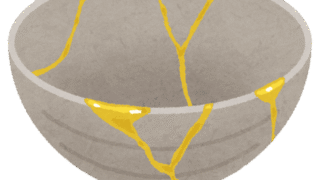 学ぶということ
学ぶということ  学ぶということ
学ぶということ  学ぶということ
学ぶということ 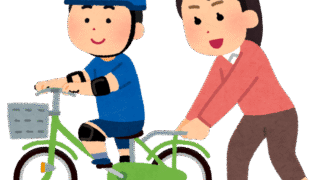 学ぶということ
学ぶということ  学ぶということ
学ぶということ  学ぶということ
学ぶということ  学ぶということ
学ぶということ 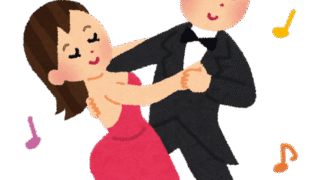 学ぶということ
学ぶということ  学ぶということ
学ぶということ