 カウンセリング
カウンセリング 治療外の効果
カウンセリングルームの外には、人を変化させる力が備わっています。日常は一定のようでいて、実はいつも変化に富んでいて、一日たりとも同じ日というものはありません。そんな揺らぎが生じているのです。そして、その揺らぎに適応しようとすることで変化が促進されていきます。
 カウンセリング
カウンセリング  カウンセリング
カウンセリング 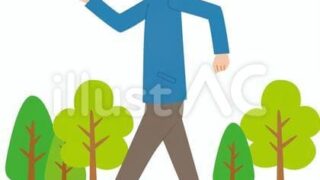 生活と心
生活と心  カウンセリング
カウンセリング  カウンセリング
カウンセリング 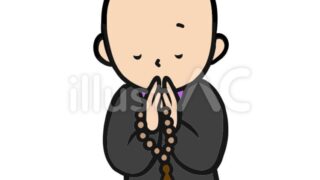 生活と心
生活と心  学ぶということ
学ぶということ 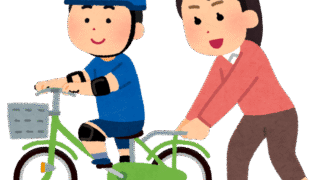 学ぶということ
学ぶということ 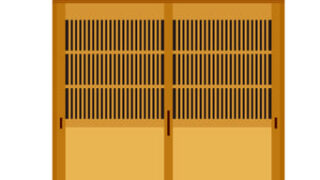 生活と心
生活と心  学ぶということ
学ぶということ