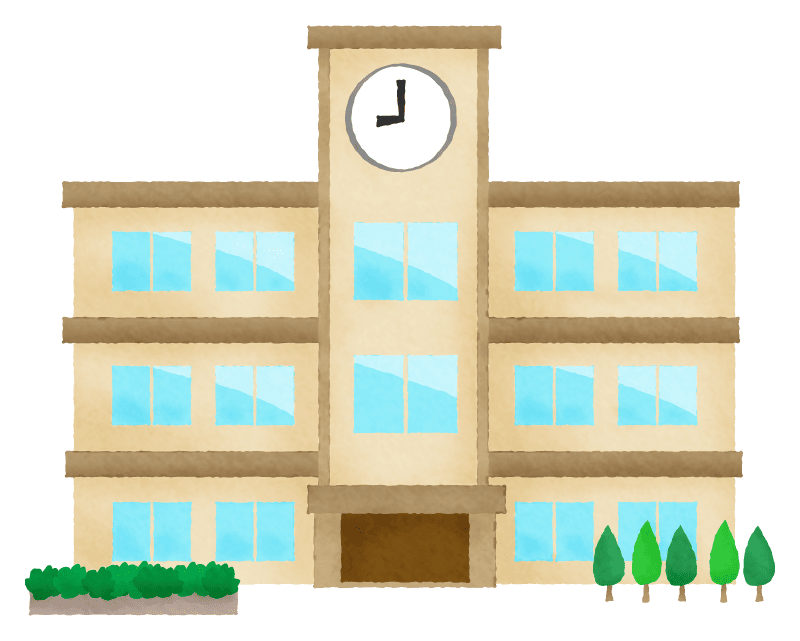2040年ころの学校
OECD は、『Back to the future of education』という報告書を2020年に出しているそうです。これは、2040年ころまでに学校がどのような道筋をたどるかという可能性について、4つのシナリオを示したものです。
各国の最近の動向を踏まえつつ、デジタル化の進展を軸にして描いています(白井俊(2025)世界の教育はどこへ向かうか —能力・探究・ウェルビーング— 中公新書)。このシナリオは、日本の学校に限定しているのではなく、世界の学校の変化についてのものです。この4つのシナリオについてまとめてみましょう。
シナリオ①:現在の延長線上にある学校
このシナリオ①は、2040年であっても、今の学校の伝統的な構造は残るだろうというシナリオです。伝統的な構造とは、教師が教えて評価するという関係だったり、一定のカリキュラムに基づいた試験があってそれによる学習評価だったりします。この辺りはあまり変わらないだろうというシナリオです。学校での評価を前提にした入試や就職の決定も、今とそれほど変わらないだろうと見ています。
変わるところは、オンラインを活用した協働作業が増えて、教科横断的な学習機会が増加するというものです。現実の社会問題に即した学習が進められるだろうと考えられています。
生徒の評価の仕方も変わると予測されています。つまり、教師は日常的に細やかなフィードバックを積み重ね、生徒の評価を教師と生徒が一緒に作り上げるプロセスが重視される、形成的評価が中心になりそうだということです。
シナリオ②:アウトソーシングが進んだ学校
シナリオ②は、教育業務の一部を民間に委託するというものです。すでに部活動は外部の専門家に委託するという流れが進行しています。この流れが加速し広がるであろうというシナリオです。
日本においては、不登校の子どもに対するフリースクールによる教育や放課後等デイサービス、民間の単位制高校など、その動きは今でも急拡大していると思いますが、それがもっと多様になるというシナリオのようです。
私的に雇った家庭教師による教育だったり、いろいろな教育サービスが生まれてくるだろうということです。教育が多様になりますから、学びの選択肢が増えていきそうです。それはメリットでしょう。
しかし、家庭環境の格差や保護者の教育への関心度によって、子どもの教育の質・量に格差が出てくることも容易に考えられます。したがって、評価の基準や評価方法などは、政府による一定の介入は必要になるでしょう。
このシナリオでは、旅行代理店のような機能を果たす新しい「教育アドバイザー」のような職種が生まれうることも指摘しています。
たしかに、教育サービスが多様になると、どんなサービスがあるのか分からなくなるので、子どもに応じた教育サービスをきめ細かく提供するための職種はあったほうがよいでしょう。
シナリオ③:地域ごとの特色化が進んだ学校
シナリオ③は、都市部、農村部、沿岸部、寒冷地域、温暖地域などの地域の特色によって学校教育が変わるというものです。たとえば、沿岸部の学校では、漁業、観光資源としての海の利用、海洋環境の保護、津波や高潮などへの防災対策などが進んだ学校です。
学校の伝統的機能は残るのですが、教師だけが指導する状況が変わって、地域の様々な専門家が教育に参入することが期待されます。授業も、学年にとらわれず柔軟な形で展開され、場所も教室や学校だけでなく地域に出ていく可能性が高まります。
今では大都市圏への一極集中が続いていますので、子どもが地元に残れるようにしたいという地域は少なくないと思います。そういう地域の特色化が進んだ学校だそうです。
シナリオ④:融解する学校
シナリオ④は、AIやVR、IoTの技術を活用して、好きな時に好きな学習ができる学校です。子どもの評価も安全管理もAIの技術が担っています。学校や教師の役目は徐々に融解し、やがて消滅するというものです。
どうしても、未来の学校を捉えるとシナリオ④のように極端なことを考えますが、2040年までにこのような技術革新が起こるのかというと、ちょっと難しい気がします。しかし、このような技術革新がどんどん進み、教育の中でも活用されることは間違いのないことでしょう。
どのような教育になるのか見てみたいものです。
結局のところ
このシナリオを紹介している白井俊さんは、①の「現在の延長線上にある学校」を基軸としながら、②③④を一定程度織り交ぜた形がこれからの学校の姿になっていくととらえています。確かにこう整理してもらえると、それが最もあり得るシナリオのように思います。
学校の普遍的な役割
同じく白井さんは、これから学校がどのように変わろうと、つぎのようなことは学校の普遍的な役割として残るとおっしゃっています。
●社会規範や伝統・文化を継承するためのプラットフォーム(共通の土台)としての学校
●民主主義社会を支えていくための基盤となる知識や教養を身につける場としての学校
●地域とのつながり、人とのつながりの希薄化の中で、教師やクラスメイトと一緒に過ごしていく場としての学校
2040年までの学校の変化を私もウォッチし続けたいと思います。