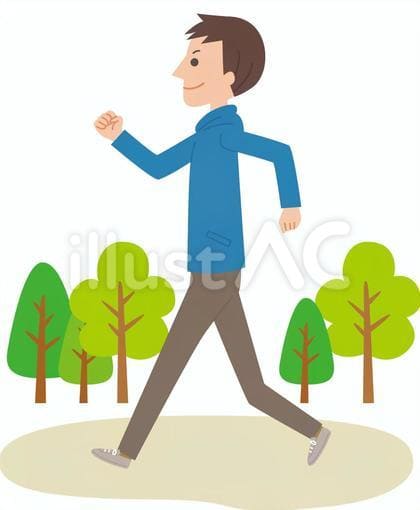散歩という日課
散歩が好きでよく歩いています。健康のためでもありますが、それよりも、ただ自然を感じたいために歩いています。スタスタ歩くというよりも、のんびり歩くことが多いです。ウォーキングというよりも散歩ですね。
視覚や聴覚、嗅覚などすべての感覚を意識して使うようにしています。キンモクセイの香りがするだとか、きれいな花が咲いただとか、そんな些細な変化を探しながら、自然と対話をしているのかもしれません。
いつも目的に向かって効率性を重視しながら仕事をしていますから、無目的で行き当たりばったりに歩く価値はとても大きなものがあります。
歩くという哲学
今年翻訳された『歩くという哲学』(フレデリック・グロ著 谷口亜沙子訳 山と渓谷社 2025)という本を読んでいます。少しずつ少しずつ読み進めています。このゆっくりペースは自分の歩くペースと合っていて気に入っています。
この中にソローの『冬の散歩』からの引用がありました。確かにそうだなと大きくうなずいてしまいました。こんな内容です。
ソロー『冬の散歩』より
「大地のふところには、自然の力によって地中に灯(とも)り続け、決して消えたことがなく、どんな寒さでも打ち負かすことのできない一つの火が存在している。[…]その地中の火は、ひとりひとりの人間の胸の中で、祭壇の火となって灯っている。なるほど、凍りつくような寒い日に、吹きさらしの丘の上にいるとき、歩行者は自分の上着のふくらみに、炉辺(ろばた)で焚かれる火よりもあたたかな、ひとつの火を抱えているものだ。実際、健康な人間は、どの季節にも自分なりに均衡をとる方法を知っており、冬のあいだは、胸のなかに夏を抱いている。そこが南になるのだ。」
冬の寒い時期に歩いていると、このように感じることは確かにあります。服の内側と外側とでは寒さがまるで違うので、自分の内側で灯る火をとても強く感じることになります。
この引用に感動したのは、自分と大地の似たような構造に気づいたからかもしれません。自分というちっぽけな存在が大地と同じ構造によって作られているのは何とも面白い対比です。
これから冬に近づいていきますが、冬の散歩が楽しみです。