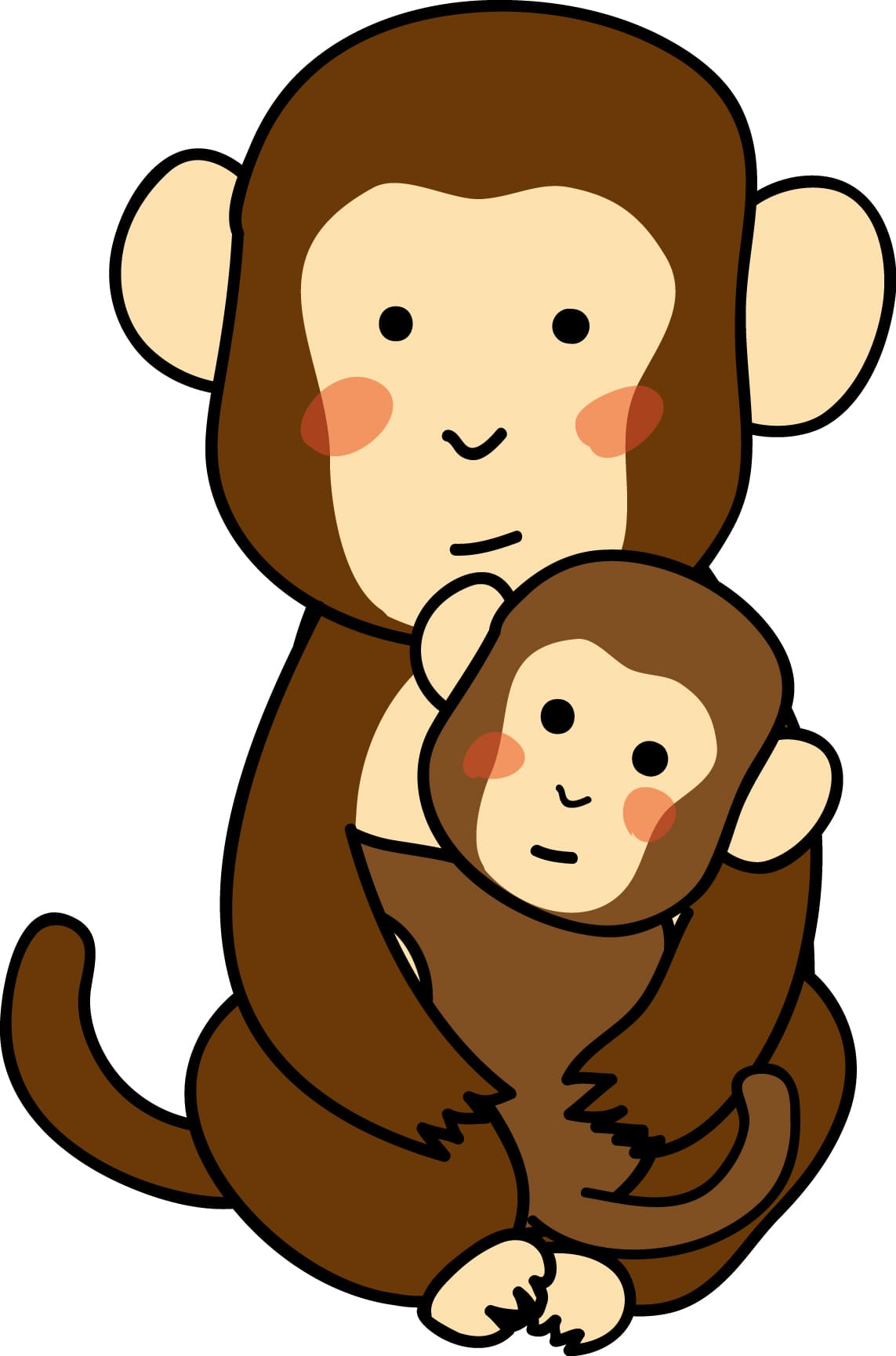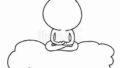ヒトの脳の動物的な面
心理療法は言葉でなされることが多いものです。言葉でのやり取りですから、理性的で論理的なコミュニケーションがなされます。そして、セラピストは言葉での対話がどのようにクライエントの心に作用するのかを考えながらかかわることになります。
セラピストとクライエントの言葉と言葉のやり取りが、クライエントの心をどのように修正していくのかということを考えるわけです。
しかし、最近は脳の研究が進んでいますので少し違った視点が導入されているようです。心理療法というのは、「動物と共通する脳の働き」として症状を理解し、「ヒト特有の脳」でそれを制御し、意識的な認識を広げることであるという考え方です。『why therapy works』ではそのようなことを主張しているように思います。
脳の誤作動
「ヒト特有の脳の機能」というのは、言語や思考を活用して現実を論理的に客観性をもってとらえたり評価したりすることです。あるいは記憶を構成して物語を紡いだりする働きのことでもあります。心理療法は、この「ヒト特有の脳機能」を活用して、誤作動を起こしている「動物と共通する脳(特に扁桃体)」の働きを理解し制御することであるということになります。
ここでいう誤作動とは、ちょっとした行き違いにもかかわらず強烈な見捨てられ不安が高まったり、安全な場所と知りながらパニック発作を起こしたりしてしまうということです。
これらの誤作動を「ヒト特有の脳機能」によって制御する方法が心理療法である、とも言えそうです。
心理学が軽視してきたこと
心理学では、「ヒト」の行動、認知、記憶などの心理学的機能を取り出して、それを研究してきました。ヒトをヒトたらしめる「human mind」を特定し研究してきたわけです。しかし、そこではあることが軽視されていました。それは「ヒトの心も動物的な脳の働きがベースにある」という事実です。
心理学は動物的な脳の働きは目を向けないまま、それを飛び越えてヒトの心の探究に向かってしまったといえるように思います。もちろん動物心理学や進化心理学という分野はあります。そして確かにこれらはヒトを動物としてとらえる観点を持っていますが、領域的には決して心理学の主流とはいえません。
非合理的信念を作り出す脳
「動物と共通する脳の部分」というのは、「非合理的信念を作り出す脳」のところで書いたようなことです。簡単にまとめると次のようになります。
- 論理性や客観性、正確性などよりも、生存できるかどうかを第一に優先すること。
- これまでのやり方が現在の生存を導いたので、たとえその生き残り戦略が不合理であったり、すでに不要になったりしていても、強力にそれを続けることによって適応や生存を目指そうとすること。
- 不安を回避するために、素早く分かりやすい説明や一面的な情報に飛びつきがちなこと。
成長するにしたがって、「動物的な脳」は「ヒト特有の脳機能」によって制御されるようになりますので、これらの傾向は弱まるものです。しかし動物的な脳の作用はバックグラウンドミュージックのように、いつまでもわれわれに影響し続けます。
脳から「生物・心理・社会モデル」へ
対人援助の世界では、「生物・心理・社会モデル」というモデルがあります。人の不調は、身体的要因、心理的要因、社会的要因が複雑に絡んでいるものなので、これらの三要因に介入することがベストな対応を作り出す、ということを示すモデルです。
この3つの要因に対して一人(あるいは一職種)で対応することはできませんので、医師や看護師、ソーシャルワーカーの人たちとの協働が求められています。
しかし、この3つの要因を「脳」という一つの視点からとらえて、目の前のクライエントの状況を理解できると、心理職なりの「生物・心理・社会モデル」の見方ができるようになるかもしれません。