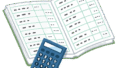自閉スペクトラム症
カウンセリングをしていると自閉スペクトラム症(ASD)の人たちと会うことがあります。この人たちは、「こだわりが強い」とか「空気が読めない」という特徴があったりします。
この特徴は、経験を積みながら成長していくと和らいでいく人も少なくありません。ただ、幼い子どもの場合はその特性が如実に出たりします。
言葉をそのまま受けとる
低学年の子どもが学校から帰宅するとき。ASDの子どもと先生のが昇降口で次のような会話をしていました。
先生:「まっすぐおうちに帰るんだよ」
子ども:「先生、まっすぐ帰るとあそこの門にぶつかってしまうよ!」
先生:「まっすぐっていうのは、道草を食わないで帰りなよ、という意味だよ」
子ども:「先生!道草って食えるんですか?どういう調理法があるんですか?」
こういう会話になってしまうのです。「うーん、この子は挑発しているのかな?」「わざとやっているのかな?」と、その真意を測りかねてしまいます。
定型発達といわれる普通の人たちは、このコミュニケーションをどのように読んだらいいのか分からなくなってしまうのですね。普通、このような会話にはなっていきませんから。
ちなみにここでいう「読む」というのは「真意を捉える」という意味です。本を「読む」とは違うものですが、幼いASDの人たちは、本を読むのが「読む」ことだと考えますから、「相手の気持ちを読む」という言葉の使い方は間違っているのではないかと不安になりがちです。
「空気をよめ」と言われても「空気なんか読めないじゃん!」と、不安とイライラを募らせてしまいます。
本人はいたって真面目
当の本人はいたって真面目です。先生を挑発したりバカにしているわけでは決してありません。
むしろ、先生を先生として認めているからこそ、その言葉にウソはないだろうと判断して、その言葉通りに素直に「まっすぐ」や「道草を食う」を受け取っているだけなのです。
学校はウソばかり教える!
あるASDの小学生は、「学校の図書室にウソの本があるのは許せない!」とイライラした様子で私に言いました。物語がたくさんあることが嫌なのです。
「だって、物語ってウソでしょう。何でウソの本が学校にあるの?学校はウソを教えたらだめでしょう。ここは学校だよ!」
こういう世界で生きているわけです。この子も市の図書館に物語があるのは百歩譲って許せるようです。しかし、”学校の図書室”に置いてあるのは「けしからん!」という気持ちがあるようです。
この子はいつも図書室で図鑑ばかりを眺めています。そこにウソはないから安心できるのです。昆虫図鑑やのりもの図鑑には、いわゆるカタログ的知識が詰まっています。言葉と写真が一対一対応していて、その解説にもウソはありません。
こだわりとは
このように図鑑に夢中になっている様子を見て、われわれは「こだわりが強い」と感じてしまいますが、ASDの人たちにとっては、そこに安心感や安らぎを感じられるようです。
ですから、この「こだわり」に見えてしまうことは、本人たちにとっては大切な心の領域だったりします。できるだけ大切にしてあげたいところです。
スペクトラムということ
スペクトラムというのは虹にたとえられます。赤や紫、青や黄色といった虹の色は、その境目が微妙ではっきりしていません。いつの間にか違う色になっています。
それと同じように、「こだわりの強さ」も「空気が読めない」のも、スペクトラムということです。その傾向がとても強い人から非常に弱い人までスペクトラムで連続しているわけです。
「ここまでは普通で、ここからはASDである」と線引きできるものではないのです。
経験を積んでいくと
こだわりやコミュニケーションは、経験を積んでいくと何となく分かっていくようです。ふつう青年期くらいになると、だれでも周りの目を気にし始めますが、それはASDの人たちも同じです。
ですからASDの人も、このころになると周囲に目を向けて、周りの人に合わせようという意識が急速に高まっていきます。いわゆる適応を目指して、”普通”を目指し始めます。
そのような苦労もあって、表面的には何となく症状は影を潜め、”普通”に見え始めることもあります。”普通”を装うことができるようになっていくのです。
ただ、根本的な特性は変わりませんので、人といるととても疲れてしまうことがあります。あるいは、この適応の苦労の過程で、不安が高まったり、強迫が高まったりして、ちがう症状が出てきてしまうこともあります。