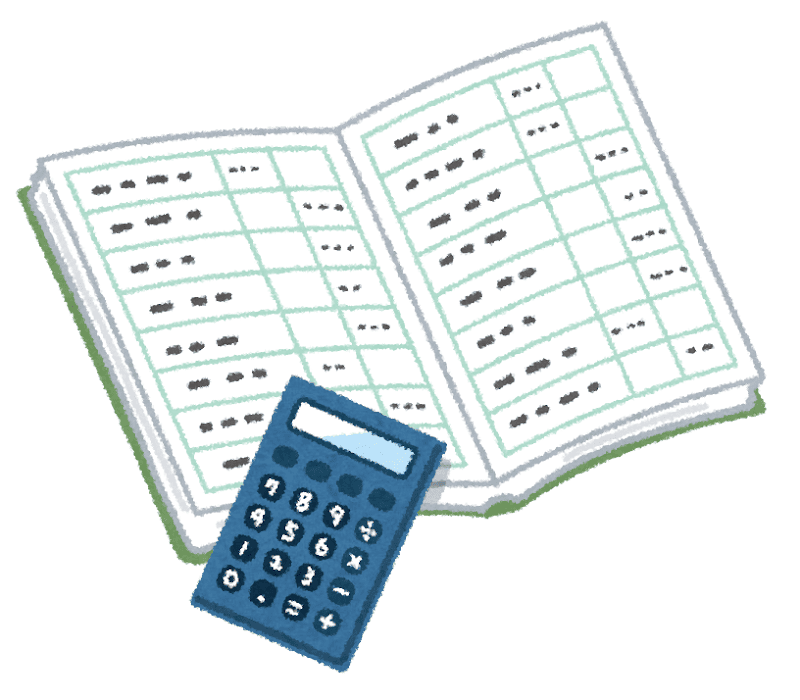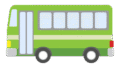前回に続いて
東畑開人さんの講演で「心を可能にする仕事」というキーワードがあったのですが、もう一つ「臨床を可能にする仕事」ということもおっしゃっていました。これについても考えてみたいと思います。
これは心の臨床を可能にするような仕事のことで、心理療法という営みそのものを継続的に保障するような活動のことのようです。
臨床を可能にする仕事
管理職としての仕事
直接クライエントと会わず、職場の心理職が安心して働けるような環境を整えたり、部下の働き方を査定したり、統計資料を作成したり、組織内の会議に参加したり、スーパービジョンの制度を整えたりと様々な仕事があります。これらの仕事は「臨床を可能とする仕事」になるわけです。
管理職がこういう仕事をしてくれるから心理職は働けます。管理職の人は、なかなかカウンセリング活動はできませんけどね。
顧客獲得の仕事
ブログを運営したり、執筆したり、講演活動をすることによって自分たちの仕事を世にアピールする仕事。これによって、困っているクライエント予備軍の人たちは、カウンセリングがどのようなものなのかいうことを知って、カウンセリングにアクセスしやすくなるでしょう。
予算の獲得の仕事
これは大きな仕事です。予算がないと働けませんから。組織内の課題を解決する資源として、心理職が認知されているかどうか、期待されているかどうかにかかっています。
周囲の専門職と上手に連携をして心理職のことを知ってもらったり、管理職としての仕事の果たす役目が重要です。
連携
組織内の会議に参加したり、他の部署の人たちと良好な連携を維持することによって、心理職の仕事の必要性を他職種の人たちにも理解してもらうことも大きな仕事です。
個室にこもってカウンセリングをしておけばそれでよいというわけではないのです。
連帯
たとえば「〇〇心理学会」、「○〇県臨床心理士会」といった学会活動や職能団体における活動です。そのような活動に参加したり、役員を引き受けて研修を企画したり、会費を徴収してその使い道を検討したり、といった様々な役割と仕事があります。
心理職同士のつながりを確保し、心理職のアイデンティティを支え、職能を高めるためのものです。心理職の連帯を深める活動と言ってもいいかもしれません。
心理職はまだまだ社会に認知されているとは言えない状況です。職場の中で心理職は一人だけという中で仕事をしている人もすくなくないでしょう。
そのため、心理職の声を世に発信することは大切なことです。あるいは、社会からの要請を受け入れて活動するための窓口も必要でしょう。
スクールカウンセラーにとっては?
スクールカウンセラーにとっても「臨床を可能にする仕事」は増えてきています。
役割を引き受けること
心理職が有識者として会議の委員を務めることがあります。スクールカウンセリングの領域では、いじめ問題調査委員といった第三者委員会のメンバーになるのも、「臨床を可能にする仕事」の一つでしょう。
カウンセリングをするわけではないのですが、行政の人々(例:社会福祉協議会、教育委員会、裁判所)や他の職種の人、地域の人に心理職の視点から物事を見ることの有効性を認知してもらうためには、こういった仕事も欠かせません。
地域コミュニティの中では対人関係にまつわる問題が増えています。そして、心理職はそのような問題を解決する資源として、自分たちが思っている以上に期待されています。
授業をすること
心理教育というものです。これは予防啓発活動であり、健康増進活動でもあります。心理的なことが問題になる前に、たとえばストレスにどう対応すると良いのか、といった知識と技能を高めるために行われれる教育です。
心理教育は、昨今の学校ではスクールカウンセラーが担うことも多くなっています。
「臨床を可能にする仕事」の増加
心理職の活躍の場が増えていくにつれて、心理療法という仕事だけをしていればいいという時代はすでに過去のものになっています。
むしろ、「臨床を可能にする仕事」の方がどんどん増えているのではないでしょうか。それは心理職が世に認知され社会から求められているという証拠でもあるように思います。
大学院では教えられないことなのですが、社会に出るとすぐにこういうことが求められるようになるということは、大学院生たちにもしっかりと伝えておかなければならないと思っています。