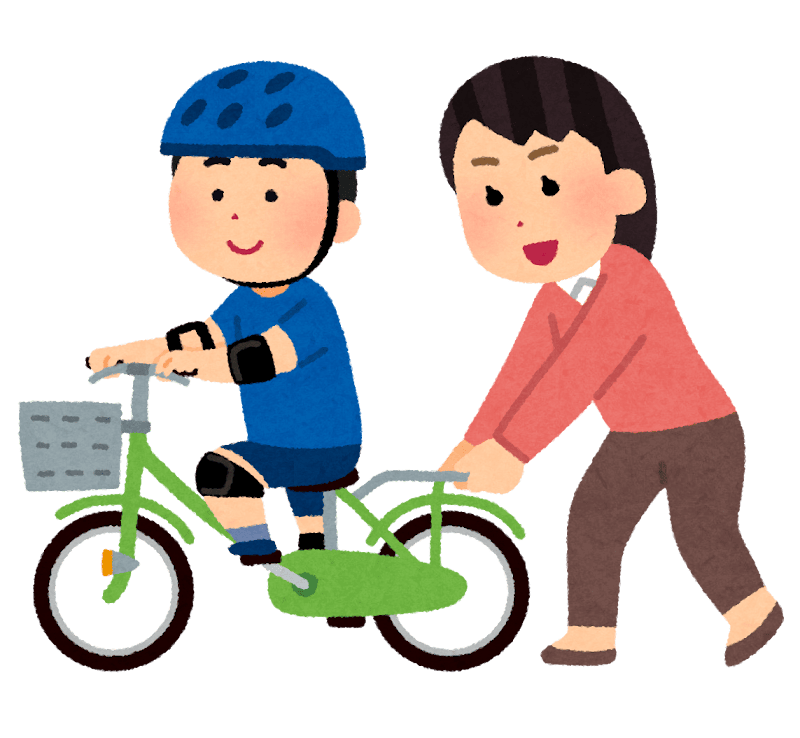練習と成長
学校で働いていますから、子どもたちが練習している場面をよく見かけます。逆上がりの練習、漢字練習、計算練習、楽器の練習。たくさんあります。そして、だんだんと上手になります。
練習すると効果が表れるわけですが、この効果を説明する言葉として「マクロ化」と「並列化」、「環境のリソース化」があります。
『私たちはどう学んでいるのか』(鈴木宏昭,2022,ちくまプリマ―新書)で解説されています。
マクロ化
これはミクロからマクロに認知や行動が変わっていくということです。漢字練習で考えればすぐにわかります。小学校1年生が最初に漢字を覚えるときは、一画書いては手本を見て、次の一画を書いてはまた手本を見てということを繰り返します。ミクロの動きをするわけです。
しかし、これが練習を重ねて熟達していくと、どんどんマクロになっていきます。「サンズイにアオ」と言えば「清」であることが分かったりします。板書を書き写すのも楽になっていきます。一画一画を一つずつ調べる必要はありません。
自動車の運転技術の向上プロセスも同じですね。最初はルームミラーを確認してブレーキを踏んでエンジンをかけてと、やることがミクロに区切られていて、それに一つ一つ対応します。しかし、熟達していくとこういうことは自動化されて、”運転”という中に含まれてしまいます。意識の外(非意識)で働くようになるのです。
簡単に言うと、いちいち確認しなくても一挙にできるようになるということです。
並列化
これは別々の作業を同時に行えるようになることを言います。「運転しながら会話をする」といったようなことです。「スマホを操作しながらご飯を食べる」といったことも並列化の例と言えるでしょう。
スマホ操作が苦手な人は、それだけに集中して、食べる動きはストップしてしまいます。
環境のリソース化
われわれの行動や認知はかなりの部分、環境に支えられています。パソコンを上手に打てるようになるには練習が必要です。その時には、キーボードの位置や高さを最適化しなければなりません。
つまり、キーボードを素早く正確に打てるようになるための環境を作り出す必要があるわけです。スキルが働きやすいように環境を変えられるようになるわけです。
身体も環境
このとき、自分の身体も環境になります。私はあまり使わないPCのキーボードを打つときには、まずは左手のポジションを確認します。そうするとその左手の位置が環境となって、考えずとも右手は最適な場所に瞬時に動きます。
大谷選手がバッターボックスに入るときは、まず左足の位置を確認してそこを固定します。そしてこの左足が環境となって右足や身体全体の位置が決まっていきます。身体も環境なわけです。
私の領域でいうと、心理検査の練習を重ねれば重ねるほど、このような効果が表れてくるのだと思います。