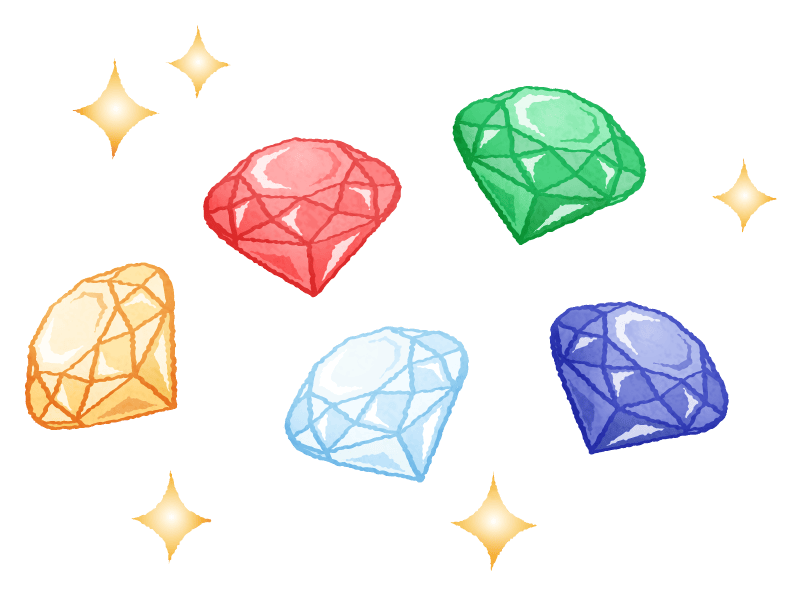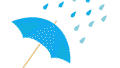リソース
クライエントの人たちと話すとき、私は「あなたをポジティブな気持ちにさせてくれることってどんなことですか?」とか「どのようなことが好きなの?」とか、「どういうことをしているときが一番落ち着く?」といったことを質問するようにしています。
すると「〇〇のキャラクターが好き」、「〇〇先輩に憧れている」、「○〇をしていると気分が落ち着く」と様々なことを話してくれます。こうすると、「問題維持システムから治療システムへ」と話が展開していくことが多いものです。
この○〇のことを「リソース」といったりします。リソースとは資源のことです。心の回復の資源になる、エネルギーになるようなものです。心の健康の維持増進にかかわる大切なものです。
問題もリソース
一般にリソースとは、好きなことや楽しいことあるいは得意なことです。当たり前ですが、クライエントを悩ませている問題や病気からは切り離されていて、そこから距離のあるものだと思います。
ところが、「問題」とリソース(資源)を切り分けるなと唱える人がいます。「問題でさえ有益な資源である」という考えです。『ブリーフセラピーの極意』(森俊夫著,2015,ほんの森出版)という本に書かれていて「へー」と思ったので書いておきたいと思います。
この発想は、元をたどれば催眠療法で有名な精神科医ミルトン・エリクソンによるそうです。エリクソンは患者さんとのかかわりで次のような有名な事例があるようです。
宗教血統妄想のある患者
エリクソンが診察している患者さんに宗教血統妄想のある統合失調症の人がいたそうです。この患者さんは「自分はイエス・キリストの生まれ変わりである」ということを本気で信じていました。普通だったら、この妄想は問題として認識されるでしょう。
しかし、エリクソンはこの妄想を使ってこの患者とかかわっていきました。次のような感じだったそうです。
「君はイエス・キリストの生まれ変わりだよね。だったら大工道具が得意だよね。ちょっと医局の本棚を直してくれない?」
当然、この患者さんはイエス・キリストが大工だったということを知っています。自分がイエス・キリストである以上、本棚を直すことなんてお手のものでしょう。この患者さんは「わかった」と同意したそうです。
本棚を直すためには、道具をそろえたり必要な物品を手に入れなければなりません。作業を進めるためにはかなり現実的な能力を発揮しなければなりませんので、妄想状態になっているひまはなかったと思います。
次のお願い
それが終わったら今度は、「君は人々を救うのがミッションだよね。じゃあ、ほかの患者さんと協力して、みんなで病室のモルタルを塗り直してくれない?」とお願いします。患者さんもイエス・キリストですから断るわけにはいきません。また「わかった」と同意しました。
こちらは本棚の修繕よりもさらに難易度が高いでしょう。どんな壁の色にするのか、モルタルの量をどの程度手に入れればいいのかなど、やはり現実的なことをいろいろ考えなければなりません。
仲間を募る必要もあります。さてどのように説明して仲間を募るか。作業が始まったらリーダーシップを発揮したり、協力者たちからああだこうだと言われて、それにも対応しなければならなかったでしょう。
こうしてエリクソンは、「自分はイエス・キリストの生まれ変わりである」という妄想を使って、この患者さんを社会復帰にまで導いていったそうです。
ユーティライゼーション(utilization)
エリクソンは目の前にあるものは何でもリソースになると考えていたそうです。そして、使えるものは何でも使って治療に役立てようとしたそうです。エリクソンにとっては問題ですら資源なのです。このように目の前にある資源を開発して活用する・利用するという発想をユーティライゼーション(利用)と言います。
ミルトン・エリクソンに師事していたザイク(Zeig)という人は、ユーティライゼーションを「治療場面に患者がもち込むものや存在するものは何でも利用すること」と言います。「言い換えるなら、利用とは、患者や環境のいかなる側面にも戦略的に反応しようとする治療者の準備性のことである」(ザイクほか『新装版 ミルトン・エリクソン』2019、金剛出版、p.66)と説明しています。
戦略的とは
診察室に入ってくるなり走り回っている子どもがいたそうです。座って診察などできそうにありません。エリクソンは、その子を制止することはありませんでした。なにせ、患者のいかなる側面にも戦略的に反応しようとする準備性が整っていますから。それでは、エリクソンはどうしたのか。
その子の動きに合わせて、「君はこっちに走ってきているね、君はあっちのドアに向かって走っているね、こっちのドアに走っているね」といった具合に、子どもの動きに合わせて声をかけていきます。
ちょっと普通ではない変わったかかわりですが、これには戦略がありました。
そうしていると、次第に子どもは、エリクソンが次にどこに向かって走ると言うかを待つようになったそうです。つまり、エリクソンに注意を向けその言葉に耳を傾けるようになったのです。そうやって子どもとのコミュニケーションを作り出すとともに、子どもの話すモチベーションを整えていったというわけです。もちろん、エリクソンはこうなることを狙っていたのだと思います。
これも走り回るという動きを利用しながら、戦略的にかかわっていき、話ができる状態にまでもっていった例と言えるでしょう。私は「戦略的」ということを、今、目の前のクライエントさんがもち込むものに乗っかって、ある程度の落としどころを想定しながらかかわることだと理解しています。
エリクソン関係の本を読んでいると、この戦略というのは奇抜な方が効果的なようです。相手に「はあ?」とか「おや?」と思わせるようなかかわりです。
奇抜ですから、やろうと思ってもなかなか難しいですし勇気もいるように思います。それを可能にするセラピストの遊び心と枠にはまらない自由さが大切な気がしています。