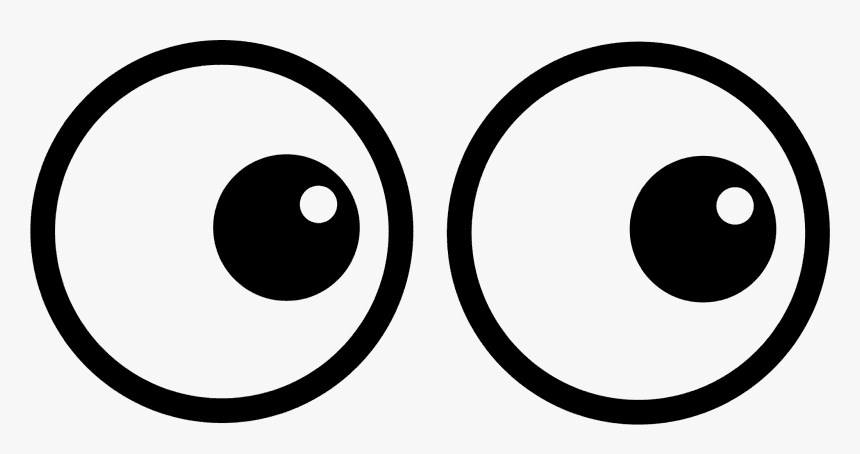夫婦で来談
スクールカウンセラーをしていて、年に1回くらいですが、夫婦面接を行います。お父さんとお母さんが子どもの相談でやってくるのです。
そういう時に外していけないポイントがあるそうです。東豊先生がおっしゃってました。
それは、一方がしゃべっているときは、必ずもう一方の表情を見ること です。これに尽きるそうです。
例えば、お母さんが話している時には、お父さんがその話に乗っているか、それとも乗っていないかといったことを見ておくのです。事例として書くときは次のようになるそうです。
母:「うちの子は、学校には行きたがらないんですが、優しいところがあって、よくおばあちゃんのことを気に懸けて、おばあちゃんの家に行ってくれるんです(夫:ニコニコした表情)」
このト書き部分をしっかり書いてあるような事例は、それだけで優れているそうです。というのは、この後のセラピストの反応は、このト書き部分に合わせていくことになるからです。
ト書きに合わせる
ト書き部分が(夫:ニコニコした表情)とあれば、セラピストはそれに合わせて、「それは優しい子ですね」となります。そのお母さんの話に肩入れすることに問題は起こりません。そして、「お母さんはこうおっしゃっていますけど、お父さんはどう思われます」と返していくと、「その通りです」となりやすいでしょう。これがこの夫婦にジョイニングすることになります。
ト書き部分が(夫:表情が曇って険しくなる)とあれば、セラピストは母の発言に肩入れすることはありません。「そういうお子さんなのですね」とフラットに返して様子を見るようです。どのようにジョイニングするかの観察を続けることになるでしょう。
このことは、相手が夫婦のときだけでなく、先生が複数人いるときなども応用できると思います。
このセラピーの対象者は誰?
学校に対して夫婦で文句を言っていて、カウンセラーにも会いたがっているという保護者の方もいます。この場合、”学校 対 保護者”に巻き込まれている構造です。このような場合、このセラピーの対象は誰かということを判断しなければなりません。
来談しているのは夫婦なのですが、この夫婦と会ってほしいといっているのは学校ですから。
ひと手間の調整
このような場合、調整が必要になるでしょう。学校側には「おろらく夫婦は学校を悪く言うと思うけど、まずはその保護者に合わせて聴くことになるけどごめんね」をしておくのです。そしてその了解を取っておくことです。
この場合、学校側もセラピスト側の気持ちを汲んでくれるでしょう。このようなひと手間かける調整をしながら仕事をすることが、コラボレーションには必要になると思います。
そうしておけば、保護者との面接の中で、安心して保護者のニーズにジョイニングすることができそうです。