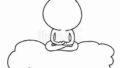『論語』の言葉
「一を聞いて十を知る」ということわざは、賢い人を形容するときに使う言葉です。確かにこういう人っていますよね。頼みごとをちょっと伝えただけでパッと理解して、求めることをしてくれる人。「よくここまで私のやってほしいことが分かりましたね」と、思わず感心します。
この「一を聞いて十を知る」は『論語』にあるそうで、孔子の弟子の子貢(しこう)という人の言葉のようです。この子貢が、同じく孔子の弟子の顔回(がんかい)という人物がいかに優れているのかを語った時に、この言葉を使ったそうです。
子貢は、顔回に比べると「自分なんか一を聞いて二を知る程度だ」ということも語っていたようです。
脳内神経処理
最近はまっている『why therapy works』によると、脳の活動の90%は脳内での処理に使われています。外部に注意を向けたり、刺激を見たり、聞いたりということに集中するのはおよそ10%だけです。
なぜ、10%しか外部処理に使われないのでしょうか。それは情報処理にかける時間をできるだけ短くするためのようです。処理速度を上げるために90%が内部処理に使われているのですね。どうしてそんなに素早く情報処理をしなければならないかというと、そうしないと人類は生き残れなかったからだろうとのことです。
脳は情報を短時間で処理するために、いろいろな能力を進化させてきました。
予測を立てて処理する
一つ目は「予測を立てて処理する」です。これは当たりをつけて情報を処理することで、「次はこうなるだろう」、「これはこういうことだろう」という構えで、予測を立てながら処理するということです。
予測をつけるために、脳は、これまでの経験から作られたテンプレートをあてはめて、情報処理をします。そのテンプレートが適切であればあるほど、かなりの情報処理を省けますから、より迅速な意思決定ができて、次の行動にパッと移れます。生き残り戦略としてとても優れているようです。
しかし、当てはめたテンプレートからズレる部分もありますから、間違いや誤解も生じます。しかし、それを犠牲にしてまでも素早く判断し、動くことを脳は重視します。このようなクセがあるので、われわれはあまり考えずに動いたり判断してしまうようです。
正確さより適応性
二つ目は、「正確性より適応性」の重視です。脳は外界を正確に認識するために働いているわけではなく、適応するために働きます。環境の変化や敵への対応がうまくいけば正確でなくてもそれでいいのです。
クマが出るという山道で前方の草の動きがなんだか変な様子だったらパッと逃げた方が良いでしょう。正確に何が起こっているのかを理解する必要はありません。
「あの人があなたをバカにしていたよ」と聞いたら、ムッとするのも当然のことです。そのうわさ話の正確性より先に、まずは攻撃される(=生存が脅かされる)可能性に身構えてしまうわけです。
迷わず動く
そして三つ目は「多少間違っていても信じる」です。あたりをつけて外部を処理し、正確性よりも適応性を重視するだけではまだ足りません。
「正確さ」を犠牲にしてまでも、生き残るために行ってきた素早い判断ですが、それを信じないことには素早く動けないからです。判断に迷いがあってはいけないのです。素早く動くためには「迷わず動く」が必要です。
迷わず動くために
「迷わず動く」ためには、自分の判断を正当化して合理化しようとする傾向が必要です。自分の判断を正しいと確信できていれば、素早く冷静に動けますので、次に多少のことが起ころうとも有効に対処できる可能性を高めるでしょう。
その判断が他者から称賛されれば、さらに確信できますので、脳は自分の判断を他者に認めてもらおうとします。こうして、自分の認識不足や間違いに目をつぶって、自分の判断に確信が持てるのです。そして、その脳の傾向が、われわれ人類を今日まで生き残らせてきたのでしょう。
心理療法への示唆
こう考えると、もともと脳は、1を聞いてパッと10を理解したがる傾向があるようです。そこに正確さが伴っていたら顔回のようになれるのかもしれませんが、なかなかそうはいきません。
われわれカウンセラーは、素早い情報処理をしたがる脳、正確さを犠牲にするのもやむなしとする脳、自分の判断を正当化しがちな脳、を相手にしているように思います。
心理療法は、素早く反応しがちな自分と一瞬でも間(ま)をおけるようになったり、自分の人生のストーリーを正確さに基づいて語り直したり、頑固な自己正当化を解除するといったような、人生の学びほぐしをする機会だと言えそうです。