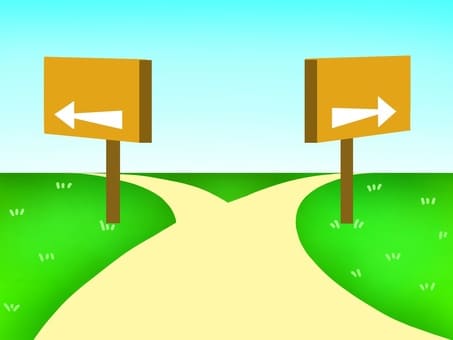来談意欲
カウンセリングを受けようと思う人は、何らかの不安や不満、恨みの気持ちなどを持っていて、これをどうにかしたいと考えています。変化を求めているわけです。その気持ちを来談動機とか来談意欲などと言います。
しかし、人は変化を望まないものでもあります。以前、そのことを書いてみました。
かいつまんで言うと、脳は適応を目指しているからです。たとえ現状に不安があり不満があったとしても、その不安・不満状態でこれまで何とか生存してきた以上、脳はその不安・不満のある状態を含めて、生存にとって必要なものと判断しがちです。
その不安・不満状態があったからこそ今まで生き残ってこられたのだと、その状態に適応しているわけです。
「変化」への不安
お金や時間をかけて変化を求めるのがクライエントさんです。こんな苦しい状態はもう嫌だ、こんなみじめな状態から解放されたい、という思いがあることは間違いありません。
しかし、だからと言って、すぐに変化に向かって歩むことは、なかなかできるものではありません。繰り返しになりますが、それがどんなに苦しい状態であっても、その状態に適応して生き延びてきた以上、その状態から離れることに対して、脳はどうしても危険を察知してしまい、それがいわゆる治療への抵抗と言われる現象を生み出してしまいます。
「変わりたい」と”ヒトの脳”は考えていますが、「変わって危険にさらされたらどうするのだ」という”動物の脳”が抵抗するわけです。
役に立ちたい
われわれカウンセラーは、クライエントには来談意欲があると考えがちです。相手にも仕事があって忙しく、お金もかかるのに、そこを何とかやりくりして、わざわざ来談してくれているわけですからね。
だからこそ、クライエントの役に立とうと思って、カウンセラーはどのようにしたら今の状態から抜け出させて、より楽と感じられる方向に援助できるかを考えます。
できるだけ早くそれをしたいと思ったりすることもあります。しかし安易にその方向に進むのは危険です。
分かれ道
お金を払って来てもらっている以上、早く役に立って変化を促進したいと考えるのは普通のことかもしれません。しかし、ここにカウンセリングがうまくいくか行かないかのポイントがあります。
「クライエントは変化を望んでいる」という前提を置いてしまうと、カウンセラーは変化を促そうと急いでしまったり、強引になってしまうことがあります。
そうすると、クライエントさんが納得する方向にいかないこともあります。カウンセラーは、”動物の脳”が納得するように対応していかなければならないのです。
最初に見立てるべきこと
そこで、最初に見極めるべきことは、クライエントは「変化したいのか」それとも「変化したくないのか」のところです。
”変化したい”は前提なのですが、「本音のところはどうなんですか?」というところですね。ここに時間をかけて、ゆっくり丁寧に確認して見極めていく必要があります。
あわてて「変化したいの?それとも今のままがいいの?」などと迫ることは決してありません。
来談経路を聞く
そのためには来談経路を詳しく訊くことがとても大切になります。来談経路というのは、どうやってこの相談室までたどり着いたのかということです。電車で来ました、バスで来ましたという話ではありません。
「この症状を抱えながら、これまでどう対応してきたのか」、「どういう工夫をして今日までやりくりしてきたのか」、そして「なぜ今、うちのカウンセリングを受けようと思うように至ったのか」というところです。
来談に至るまでの苦労や葛藤、してきた工夫や治療、助けてもらってきた経験などのことです。来談経路を聞きながら「本音のところ」を探っていくわけです。
変化への濃淡を見立てる
クライエントは、「実はもう変われないと半分あきらめている」、「これ以上頑張ることはできないと思っている」、「以前よりもずっと安定しているので、今のままでよいと思っている」、「もし変われるなら変わりたい」、「変わるための手立てを教えてほしい」などと、その変化に向けての濃淡が一人一人違います。
そこで、「本音のところ」を見極めたいわけです。
変化したい場合
変化したい場合は、すでに何かを試してみたり、工夫をこらして対応してきた歴史があるはずです。ですから、その歴史をよく尋ねて、うまくいったこと、うまくいかなかったこと、を聞いていきます。
なぜそのような対応をしようと思ったのかといったことを尋ね、その苦労や工夫をねぎらいながら傾聴したいものです。
そして、そこから比較的うまくいったことに注目し、それがなぜうまくいったと思っているのかということを訊いていくと、その人の強みが分かってきて、これからどうすればよさそうかというアイデアもわいてきやすくなります。
現状維持でよい場合
変化したくない場合というのは、どこかで現状に満足しているわけです。それなりの工夫や苦労をして、それなりに納得できる現状を作り出してきたわけです。
そういう人には、どのようにして工夫や苦労を重ねて、現状にたどり着いたのかを訊き、その時にどのような力を発揮してきたのかということを理解していきたいものです。
そしてそれは、ノーマライズすることになり、クライエントさんにとって納得感のあるカウンセリングになっていくように思います。
苦労ばかりを語る場合
もちろん、これまで全くうまくいかないといって、工夫してもうまくいかず苦労ばかりだ、それも仕方がない(ので変わるはずはない)という人もいます。
苦労ばかりを語る人は、まちがいなく都度、乗り越えてきたわけですから、そこを聞きたいところです。そのような人は、苦しみからリカバリーストーリーを豊富に持っている人ですからね。
そのストーリーの中には、必ず工夫や気持ちのコントロール、そして相手への気遣いなどがありますので、そこを探しながら訊く(聞く)感じです。
そうやって苦しい中でも実際に行ってきた工夫や気持ちのコントロールをねぎらいながら、その中でも少しマシだった時やうまくいったことを探していきたいところです。
そうすると、そのクライエントさんがどの方向に向かって、どうすればいいのかというアイデアが浮かんできやすくなります。
ジョイニング
このようにして、クライエントにジョイン(join)するのです。システムズアプローチという家族療法の考え方では、クライエントシステムへのジョイニングと言ったりします。
来談経路を聞きながらジョイニングするということは、心理療法を短期で有効に行う上でのポイントになります。来談経路は詳細に聞いてクライエントと一緒にセラピーの方向を考えていきたいものです。
そして、カウンセラーは、変化の方向でも現状維持の方向でもどちらでもいいから、それはクライエントが決めて、というくらいの心持ちが良いのかもしれません。
そのためには「クライエントの進みたい方向に一歩下がってリードする(lead from one step behind)」心持ちでいたいものです。