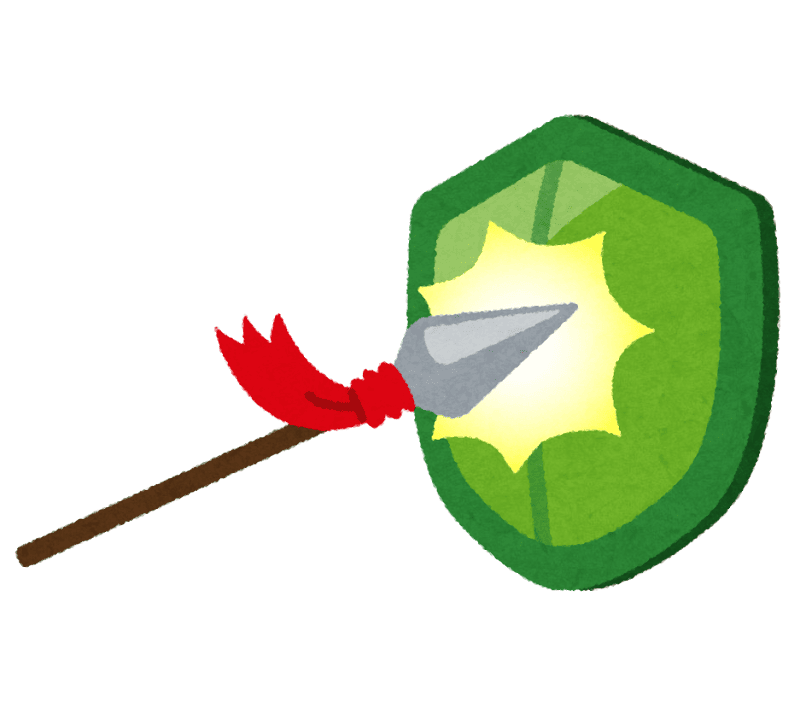偶然の成功体験
たくさんのクライエントさんとカウンセリングをしてきました。ときどき、自分でもよくわからないけれども「とてもうまくいったな」と思うケースがあります。こういうケースは、ずっと心に引っかかっているものです。
そして、あとになってからそれが心理療法の技法であったことを知るのです。「へー、そうだったんだ!」とずっと後になってから納得したりします。
あるケース
そんなケースを思い出しました。少し脚色しながら書いてみます。
ある女子高生とカウンセリングをしている時でした。この生徒は、母親と仲が悪く、いつも大喧嘩をしてしまうという主訴でやってきました。
養護教諭にも相談していたらしく、その勧めもあってカウンセリングを受けようと思ったそうです。さっそく話を聴いてみると、昨夜のけんかがとても大きく、最後はこの生徒が包丁を持ち出すという騒ぎにまで発展したとのこと。
この生徒も、包丁を持ち出すほどになってしまったことを後悔していました。後悔というよりも、そんな自分が怖くなったと言った方が正確かもしれません。
養護教諭との相談
本人によると、普段は普通の親子関係か、それ以上のよい関係だそうです。とはいえ、毎日けんかをする仲でもありました。
ときどき話を聴いてくれていた養護教諭は、「仲が良いからけんかもできるんだね」と言っていたそうで、本人も「そうだな」と思っていたそうです。
しかし、昨晩のことを思い出すと、ちょっとまずいのではないかと思って来談に至りました。
けんかの様子
けんかのきっかけや様子を聞いてみましたところ、きっかけは些細なことです。たとえば、部活動で疲れて帰宅した時。もう眠くて仕方がないので、「ご飯を食べないで寝ていい?」と母親に尋ねるのですが、母親からは「せっかく作ったのに、いいわけないだろう」、「お前は間食ばかりしてるからぶくぶく太るんだ」などと言われるそうです。
するとこの生徒もカチンときて言い返します。「私が太っているのはあんたの遺伝子だろう。そっちの方がよっぽど太っているよ!」、「惣菜ばかりで料理なんかしていないくせに!」。お互い言いたい放題といった感じでした。
本人の悩みの本質
そんな話を聴いていき、次第に本人が何を望んでいるのかが明らかになっていきました。それは、「けんかをやめたい。それができなければ、けんかするとき、暴言を吐いたり包丁を持ち出すのではなく、言葉で伝えたい。でも、お母さんには言いたいことが言えない」ということ。
「いやいや、言いたい放題言っているよ!」とツッコミを入れたくなりましたが、本人はいたってまじめな顔です。
気を取り直して「では、けんかしている時、あなたがお母さんに本当に言いたいことってどんなこと?」と尋ねましたが、「うーん、分からない」ということでした。
そこで、次のような提案をしてみました。
カウンセラーの提案
「あなたは、いつもはお母さんと普通かそれ以上に仲がいいんでしょ?(はい)。でも、けんかの時には言いたいことが言えなくなるんだよね?(そうです)。そして、極端なことになると、包丁を持ち出すほどになってしまう(ですね)。つまり、本当に言いたいことが言えない時って、まさにけんかしている時だよね(はい)。だから、まさにけんかの最中にこそ、本当に言いたいことを考えるチャンスがあるんでしょ(はあ?そうですかね?)。そうだよ、今みたいに冷静なときに『本当は何を言いたいの?』って考えても出てこないんだからさ(あーたしかに)。」
そして、一呼吸、間を置きます・・・。
「だから、けんかは止めちゃダメ(えー!)。むしろ、けんかをしている時は、チャンス到来!と思った方がいいね(へえーふふふ)。そして、そのけんかの真っ最中に、本当に自分が言いたいことはどういうことだろう、と考えるの(あー)。もちろん、このけんかは、『本当に自分が伝えたいことは何だろう?』を考えるためにやるんだよ(はい)。だからいつもの全力投球でけんかしてはダメ。それじゃあ、考えられなくなるからね(ですね)。むしろ、いつもの80%~90%くらいの力でけんかをするの(はい)。120%になっちゃうと包丁騒ぎになるから気を付けてね(はい)。どうだろう、できそう?」
「いやー、自信ないなあ、私、うまくけんかできるかなぁ」。
「君ならできる!毎日けんかしているって言っていたじゃないか。毎日チャンス到来だよ。今日失敗しても明日があるからね。がんばってね(いやー・・・)。」
「あのね、80%くらいでけんかするにはコツがあるんだよ。聞きたい?(ぜひ)。それはね、こっちからけんかを吹っ掛けるの。その方がこちらのペースでけんかできるからね。やっぱり、自分のペースでけんかすると、気持ちが整っている分、多少冷静でいられるからねぇ。あくまでも考えるためにけんかをすることを忘れずに。お母さん側から吹っ掛けてきたら、まず、ちゃんと『チャンス到来!』って心の中でつぶやいてね(分かりました)。そして、本当に言いたいことを考えるんだよ(わかりました。やってみます)」
いやー、この日の私は絶好調でした。
1週間後
「先生、うまくけんかできませんでした」
「どうして?毎日けんかしていたじゃない」
「いやー、なんか調子が狂っちゃって。お母さんも先週は穏やかだったし。」
「そういうときこそ、こっちから吹っ掛けないと」
「やろうとは思ったんですけど、タイミングがうまくつかめなくて」
「そうか、まあ、仕方がない。そのうちチャンスが来るだろうから、その時を待つか」
といった感じでした。その日のカウンセリングは、家が比較的穏やかだったことや楽しかったこと、学校でちょっと困ったことが起こったけどうまく対応できたことなどの話で終わってしまいました。
この日は最後にまたけんかの宿題を出して終了です。
さらに1週間後
「やっぱりうまくいきませんでした。いや、私も頑張ってけんかしようと思ったんですよ。でも長続きしなくて。ちょっとした言い争いで終わってしまう。」
「そうか。じゃあここ2週間くらいは、たいしたけんかはしてないってことなのね?」
「してないですね。先生、別にけんかしないでもいいんじゃないですか?なんか、もうお母さんとはけんかしないで済みそうな気がしてきました。」
といった感じで、また日常の話に展開していきました。こういうことを繰り返しているうちに、「お母さんとの関係はもう大丈夫」とのことで、結局4回か5回でカウンセリングは終結にいたりました。
その後、時々、様子を聞いていたのですが、お母さんとは大ゲンカに至っていないということでした。
治療的パラドックス
のちに、これが「治療的パラドックス」と呼ばれる介入に近いものであることを知りました。
治療的パラドックスは、クライエントが困っている症状や止めたいと思っている行動を、やめる方向ではなくて、むしろもっとやるようにという指示を出すことです。「これ以上のけんかはしたくない」という人に対して、「もっとけんかをしなさい」と介入するのです。
もちろん、けんかが必要な理由も盛り込みます。「本当に言いたい気持ちが高まっているのは、まさにけんかの真っ最中だから」といったように。この理由なしに「けんかをしなさい」といってもうまくいくわけはありません。
こうして、けんかをすれば「本当の気持ち」を考えるきっかけになります。あるいは、「けんかを発生させられるならば、けんかをコントロールできるかもしれない」という方向に話を展開できるかもしれないですね。
もちろん、けんかをしなければしないでいいのです。今回は、このような処方によって、けんかが減るのではないか、という予感がありました。
短絡的にならないように
今回はうまくいきましたが、これは高等技術だと思います。クライエントの想いとは逆のことを要求するわけですから、かなり戦略的になされるものです。基本が大切です。ゆっくり焦らずに戦略を練るゆとりも必要でしょう。
こういう技術もあるということで、今後の仕事にいかしていきたいと考えています。