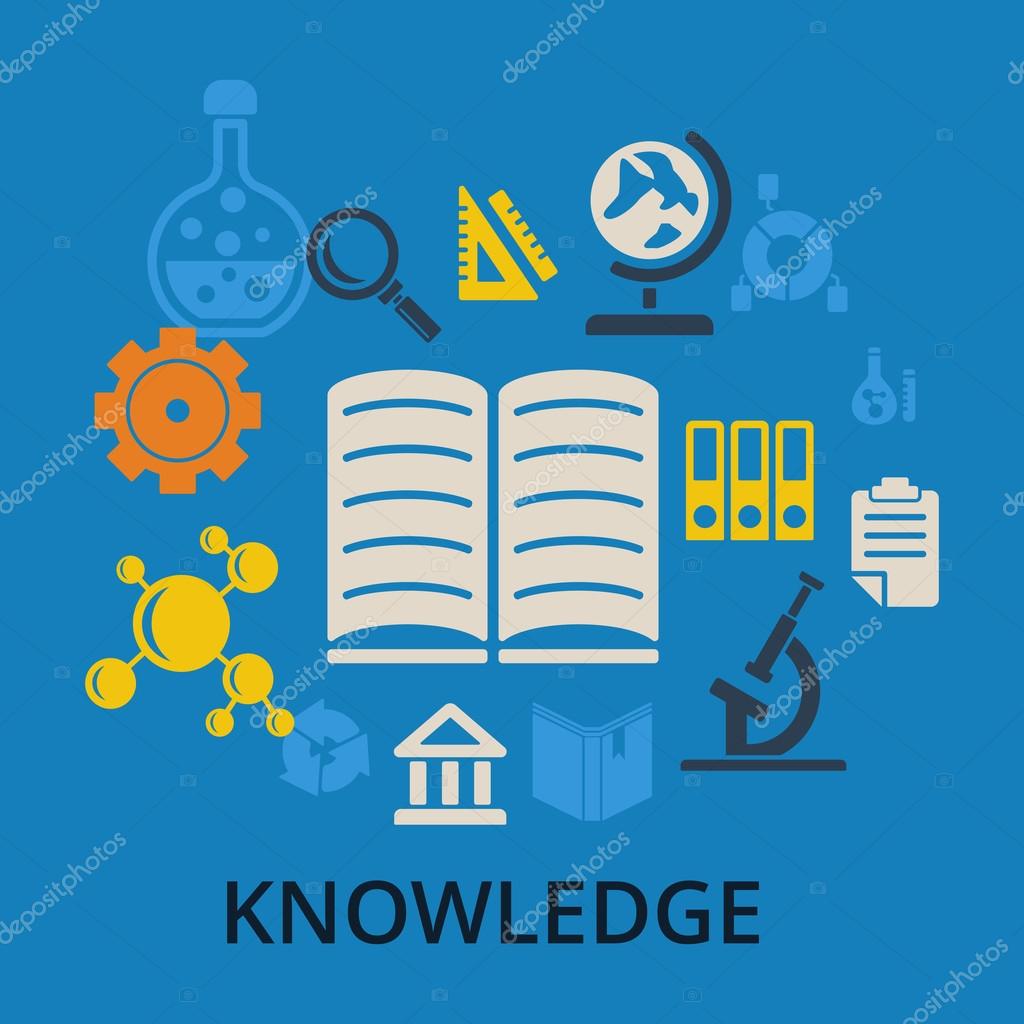モノ的知識観
知識を実体のある「モノ」のように考えるのを「モノ的知識観」と言います。たとえば、お母さんが「これはワンワンだよ。ワンワン、かわいいね」などと赤ちゃんに教えていると、赤ちゃんは「ワンワン」と覚えます。
これは「ワンワン」という知識がモノ的に赤ちゃんの頭の中に記憶されたと考えられます。知識をモノ的にとらえているということです。
モノ的知識観で説明できないこと
ただ、これはけっこう難しい問題をはらんでいます。たとえばこの赤ちゃんが、今日は昨日とはちがう犬を見たとしても、やはりそれを「ワンワン」といいます。昨日見た犬とは違う犬なのに、どうして赤ちゃんはこれを「ワンワン」と認識できたのでしょうか。
昨日見た犬の像(モノ)を「ワンワン」として記憶しているならば、今日見ている犬のことは別物と判断しなければならないでしょう。違う犬を見ているわけですから。しかし、赤ちゃんは容易にワンワンと一般化できてしまいます。
『私たちはどう学んでいるのか』(鈴木宏昭,2022,ちくまプリマ―新書)では、これをモノ的知識観と呼んでいます。
コト的知識観
この著作では、もう一つの知識観として、「コト的知識観」を推しています。赤ちゃんが昨日見た犬と今日見た犬は別物なのに、それを犬と認識できるのは、今日、その場でみた物体(犬)を「犬である」とその場で構成するからだ、という発想です。構成主義(constructivism)といいます。
五感を使って構成する
4本足で歩いている姿やむくむくとした毛並み、大きさ、揺れるしっぽや舌を出している姿、息づかいなどの入力された感覚からの情報を構成して「ワンワン」という「知識を創発」しているのだ、という発想です。
モノを探すように「昨日見た犬」の記憶を検索するわけではないのです。
創発とは
創発というのは、個々の性質を単純に足しあげた性質にとどまらない、ある全体としての性質が出現するということを表す用語です。
たとえば、気心の知れた仲間が集まると、その場にはある楽しい場が創発して、それが人々の発話を引き出すシステムとして自律的に動き出し、参加者たちはその場の雰囲気に自らを預けることによって発言が促進されることがあります。そういう場が創発します。”場が盛り上がる”、”場が引き締まる”、”場に飲み込まれる”などといいますけど、そこでいう「場」は創発されたものです。
知識の創発
知識も同じようなものです。視覚情報や聴覚情報などの個々の感覚ネットワークがリンクして「ワンワン」という知識が創発されるのです。
「ふわふわした毛」「茶色」「4本足」「揺れるしっぽ」「舌」「匂い」「息づかい」といった個々の感覚が自律的に動いて、その個々の要素を足し上げた性質にとどまらない、ある全体としての知識(=ワンワン)が創発しているのです。
「ワンワン」を記憶しているのではなく、細やかなワンワン的要素のネットワークが「ワンワン」という知識を創発しているわけです。
ほぼ非意識的な働きです。意識できるのは創発した「これはワンワンだ」というところから先です。
知識はモノとして存在しているのではなく、その場その場で創発されるのですが、このような知識観を「コト的知識観」と呼んでいます。
その領域で経験豊富な場合
この著作では、組織のマネージャーの仕事を例にとって、その領域で経験豊富な人がどのように知識を創発しているかの例を挙げてくれています。
長いですが引用してみましょう。
「マネージャーというと、計画を立て、それを部下に正確に伝え、その動向を監視し、みたいなことをやるというイメージがあるかもしれないが、事態は全く逆だ。職場をぶらぶら歩き、部下の顔を見ると、彼に頼んだ仕事を思い出し、そこで話をする。するとそこから連想的に関連した業務を思い出し、その担当者のところに出向いたりする。部下たちもそうした上司を見ることで、報告しなければならないことを思い出し、彼のところに出向く。するとマネージャーは意識の奥に眠っていたやらねばならないことを思い出す。つまりここでは、他者が環境のリソースになっており、それと触れ合うことで、膨大な数の業務リストを記憶したり、その進捗を監視するという負荷のかかる仕事を軽減させているのだ」(pp.67-68)
他者(部下、職場)が環境のリソースになって、マネージャーの知識を創発させているのです。これでマネージャーの頭の中の負荷はかなり軽減されるでしょう。
マネージャーの頭には様々な情報が記憶されていますが、環境のリソースが必要な情報を喚起して、知識を創発しているのです。情報は記憶できますが、知識は記憶するのではなく創発するのです。そういう違いがあります。
このことをベテランのカウンセラーに当てはめてみましょう。
カウンセリングの場合
この著作と似たような書き方をしてみます。
カウンセラーと言うと、心理検査によってアセスメントを行ってその心理機能を正確に把握するとともに、DSM-5などの診断基準をクライエントに当てはめて、それにふさわしいエビデンスのある治療法を選択して、それを実践しているというイメージがあるかもしれない。しかし事態は全く逆だ。クライエントの顔を見るなり、その非言語に伝わってくるものから彼の状態を推測し、それを面接に組み込もうとしたりしている。彼の話すことに耳を傾け、ラポールの形成に努めながらも、そこからリソースや未来への願い、頑なな信念やパターンのようなもの探そうとして質問もする。それに対するクライエントの語りがリソースとなって、カウンセラーは先に進むかもう少し待つか、違う視点に飛ぶかを判断する。クライエントもカウンセラーも、お互いの発話がリソースとなって、何らかの知識がおのずと創発する。思いがけない創発もある。「えっ!」と思ったり、「ハッ!」としたり、「そういえば」と想起したりして、「!」というちょっとしたひらめきやヒント、驚き、発見、記憶という知識が創発する。
カウンセリングという場でなされる対話は、クライエント一人では創発しないであろう知識の創発が肝になる。自分に関する新しい知識の創発である。クライエントが話してばかりだと知識の創発は起きにくい。良質の質問というのは、新しい知識の創発を刺激するものであり、それがリソースにもなり介入でもある。
こういう対話がカウンセリングではなされているのだと思います。