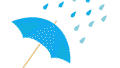事例検討会にて
ある福祉施設で働く臨床心理士の事例を聞くことがありました。セラピーがうまくいかないということで事例を発表してくれました。発表した理由は、利用者さんとの関係がうまくいかないからです。
施設の中のある利用者さんは、その施設に来ていろいろな相談をしていたのですが、次第に来談できなくなりました。やる気が出ない、睡眠不足などという理由です。
この利用者さんは、軽度の知的障害があり、一人で駅まで歩いていき、バスに乗って施設に行くということにとてもエネルギーを必要としていました。それが億劫だから施設に行くのを嫌がっている様子もありました。
その道のプロの言葉
事例発表者の上司は、長い間福祉施設で働いてきた超ベテランで、周囲の施設の人からも一目置かれているような力のある人だそうです。「この人の仕事から学びたい」と発表者の人もその背中を追いながら仕事をしてきたそうです。
その上司に相談したところ、「仕方がないから、自宅にいって訪問相談をするしかないよね、でもこれは特殊なやり方だから、自分で施設に来られるようにしないとね」とアドバイスをもらったそうです。そこで訪問相談を始めました。
アドバイスはいらない!
しかし、これがなかなかうまくいかない。相手からは「話すことはない」「アドバイスなんかいらない」と突っぱねられてしまいます。支援の手を差し伸べれば差し伸べるほどうまくいかない。そういう理由から事例検討会での検討となりました。
事例の詳細には触れませんが、確かに、いろいろな支援を考えて提供している様子には頭が下がりますが、それがうまくいかないのです。
これは現代的な大きな論点をはらんでいると思いました。
ケアの前提と支援の前提
その論点とは、「ケアと支援のちがい」ということです。実際のところは、この両者をスパッと切り離すことは難しいのですが、話を分かりやすくするために、ちょっと極端に表現してみましょう。
ケアでも支援でも、ケアする側(支援者側)とケアされる側(被支援者側)に分かれます。
ケアの関係
ケアという考え方は、「ケアする側」と「ケアされる側」は対等です。ケアする側は、「ケアする能力」があります。一方、ケアされる側は「ケアを受容する能力」があります。
この関係は、「ケアする人」がケアをして、「ケアされる側」はそのケアを受容することによって、ケアする人をケアするのです。そういう関係が”ケア”というものです。
この二つが融合するところに「ケアの空間」が創出され、その「ケアの空間」が人を癒し成長させます。
ケアは一方向的な関係ではなく、双方的で相互依存的な関係なのです。ケアする側も同時にケアされる関係になります。
支援の関係
支援の方は、高い能力を有した強く自立した個(支援者)が、低い能力しかない弱い依存した個(被支援者)を”支援”します。二者はお互いに独立しています。そして一方向的です。
目指すところは、被支援者が、少しでも能力を高め、強く自立した個になることです。依存しない個として自立することなのです。そのために能力の長けた強く自立した支援者が”支援”するのです。
このような関係を当たり前の前提として支援者が「支援」しようとするならば、被支援者の方はたまったものではありません。「アドバイスはいらない」「話すことはない」となるでしょう。
おそらくこれが、この事例の「支援」がうまくいかない理由です。
ケアの言葉か支援の言葉か
訪問相談を提案した上司の言葉は「ケアの言葉」として使われたのだと思います。つまり、「仕方がないから訪問相談に切り替えるけど、やっぱり相手もこっちに来るぐらいのことをしてくれないと、こっちもやってられないよね。一方的になったらケアにならないものね。だから、今回の訪問相談は特殊なんだよ」ということだったのだと思います。
ハッキリとこのような気持ちがあったかは分かりませんが、ケアということからすると、そのようなニュアンスの言葉だったのだと思うのです。
しかし、事例発表者は、ベテランの言葉を「支援の言葉」として受け取っていたようです。つまり、「そうですよね。やむを得ず訪問相談に切り替えるけど、それでは被支援者のためにならないですよね。被支援者も、たとえしんどくても頑張ってバスに乗ってくるくらいの強さをもってくれないと、自立できないし、そんなことでは社会でやっていけないですよね。」という気持ちで受け取ったのでしょう。
ケアの空間とサイコセラピー
心理療法とは、セラピストとクライエントが話しているだけです。心理臨床の技法として箱庭療法とか絵画療法とかプレイセラピーとかいろいろあります。
ですから、「話をするだけ、箱庭に人形を置くだけで治るのですか?」「絵をかいたり遊んでいるだけで大丈夫なんですか?」と質問されることがあります。素朴な疑問でしょう。
わたしの答えは「治ります」「大丈夫です」となるのですが、「ただし、それらをケアの空間を生み出す手段として使えるならば」という条件もつきます。
箱庭や遊びや描画には、ケアの空間を生み出す膨大な潜在力があります。しかしそれを活用してケアの空間を創出できるかどうかはサイコセラピストとクライエントとの関係性によります。
ただ、サイコセラピストは相手がどんなクライエントさんでも、それらの技法を使って「ケアの空間」を創出することに長けているのです。「ケア」を考えることは、サイコセラピーの本質的なところにつながっていきます。