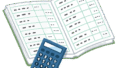講演にて
先日、東畑開人さんの講演を聞きました。著作や論文はいくつも読みましたが、本人の講演を聞くのは初めてなので、楽しみにしていました。
ちなみに、この講演の直前に、以前書いた「気」を体験していました。
彼はエネルギッシュな人で、ずっと動き回り、水分補給を欠かさず、表情豊かに話していました。楽しい講演でした。
もちろん、話す内容も勉強になりました。その中の一つに「心を可能にする仕事」というキーワードがありました。このことについて考えてみたいと思います。
デイケアの例
たとえば、精神科デイケアを例にあげましょう。精神科デイケアは、作業や活動を通して、患者さん同士の交流を促進し、それによって精神機能の維持・向上を目指します。
ですから、われわれの関心はデイケアのプログラムや想定する効果、参加者のアセスメント情報や交流の様子などに向きがちです。このことは大切なことで欠かすことはできません。
しかし、いくらデイケアの場を豊かにしたところで、患者さんがその場にアクセスできなければ意味がないでしょう。
バスの送迎
そう考えると、例えばバスを運転して患者さんを送迎する仕事も精神科デイケアを成り立たせるためには必須になるわけです。車の運転をやめている患者さんは多いですからね。
そして、このバスの送迎は「心を可能にする仕事」になります。雑用ではないのです。
心が可能になるとは?
一人で孤立している時、心はなかなか機能しません。孤立状態の中で一人考え事をしていると、内なる対話が膨らんで、一人で悶々としたり、鬱々したり、挙句の果てには悪口を言われているような気もしたりして、悪い妄想に支配されてしまうこともあります。
そんな時、ちょっと外に出かけたり、人と話をしたりすると、急に気分が変わって現実検討能力が高まります。
話題を考え、言葉を発し、相手の表情を知覚するでしょう。こちらも表情を変え、共感を示し、相手に配慮したりもするでしょう。その間、身体はうなずいたり、身振り手振りをしたりで、けっこう忙しく動いているかもしれません。
そうやって現実に目を向けて現実をしっかり検討しながら、社会の中で自らを機能させます。これが心が可能になっている状態です。
そして、これはバスの送迎があってこそ可能になるのです。ですから、バスの送迎は「心を可能にする仕事」です。
スクールカウンセラーにとっては?
それでは、スクールカウンセラーにとって「心を可能にする仕事」はどのようなものでしょうか。
掃除をする
相談室がない学校があります。その場合、臨時で場所を確保します。会議室だったり、使われなくなったコンピューター室などです。机はべたべたと汚れ、床は埃だらけ。二人で話をするにはあまりにもだだっ広い空間。そんな部屋もあります。
当然、それを掃除することは「心を可能にする仕事」になるでしょう。机や椅子が汚くて居心地が悪いということでは、心は話題に集中できないですからね。
部屋を設える
だだっ広い会議室は、机の配置を工夫して、できるだけカウンセラーとクライエントの二人が居心地よくいられるようにします。外から見えないようにカーテンを引いたり、クライエントの目線の先が雑然とならないようにします。クライエントの荷物置き場も確保しておきたいところ。
こういったことはすべて「心を可能にする仕事」でしょう。
道具を整えておく
学校では、小学校低学年の子どもやあまりしゃべらない子どもに対して、絵を描いてもらったり、ちょっとしたゲームをしたりすることがあります。
この道具をそろえるために、文具屋やおもちゃ屋に行ってモノを購入するようなことも「心を可能にする仕事」になるでしょう。私は絵葉書を送ることもよくあるのですが、これも同じです。
心理教育
心理教育では、対象者の年齢に合わせて分かりやすくストレスや感情というものを教えなければなりません。一般的に学校では、学級集団を対象として心理教育を行いますから、その学級の様子をあらかじめつかんでおくことも必要です。
同じ発達段階でも、学級の様子はまるで違いますからね。そして、学級の様子を把握するための授業観察も「心を可能にする仕事」と言えそうです。
学級の状態を把握できないままに心理教育をすると、子どもたちの心はスッと閉じてしまいます。心を動かさない方向に向かってしまうのです。
その他にも、「心を可能にする仕事」は、いろいろとあるかもしれません。
まとめ
「心を可能にする仕事」は、もう少し専門的に言うと「コミュニティ臨床」と言われる分野に位置づけられる仕事だと思います。
そして、これからの心理職の仕事にとって、心理療法というのは局所的な活動となり、だんだんとこの「コミュニティ臨床」の領域が広がっていくだろうというのが東畑さんのお考えでした。
今年の9月にこのあたりの著作が出るということですから、こちらも楽しみです。