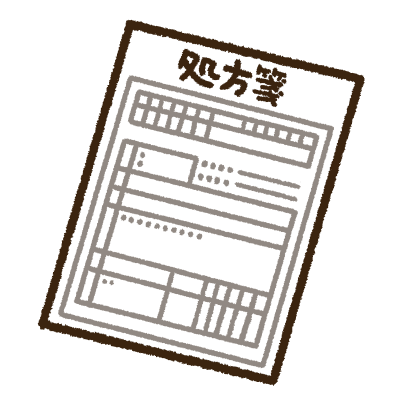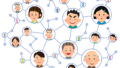診断は医師がする
私たち心理師の領域では、クライエントの心の状態を評価するときには、「アセスメント」という言葉を使います。医師でいう診断のことです。
医師が用いる「診断」という用語は、診断基準に照らし合わせて、患者さんの症状や訴えがその診断基準に当てはまるかどうかを判断することです。
そして当てはまるのであれば○〇症などと命名することです。医学が対象とする病であると認定するわけですね。
参照する基準があらかじめ設定されていて、それに当てはまるかどうかを正確に判断するのが診断です。この診断という用語は医師がする評価のことなので、心理師は使いません。
アセスメントとは
心理師の行う診断つまりアセスメントには、医師が参照する診断基準のようなものはありません。心理検査の数値やデータの解釈、クライエントとの会話を通してなされます。
このアセスメントから、クライエントの心の状態を推測するのが「見立て」です。心は目に見えませんから、”あたかもそうであるかのように”心の状態を見立てるわけです。
見立てはセラピストの仮説です。診断基準ではなく、セラピストのよって立つ理論や学派の考え方を参照しながら作られています。
そう考えると、セラピストの自由度が高いとも言えますし、セラピストの主観任せとも言えます。
見立てはセラピストのよって立つ理論的根拠に基づいて、問題を解決可能な形にクライエントの訴えを再定義する仕事です。
解決可能な形にするために
クライエントさんは、しばしば自分の問題を「人間関係がうまくいかず気分が落ち込む」であるとか、「よく眠れない」といった仕方で表現します。しかし、これでは曖昧なので、解決可能な形にするためにはもう少し詳しく事態を描写してもらう必要があります。
たとえば、「苦手な上司から自分ばかりが雑用を頼まれているようで、その負担が重く、上司に対する嫌悪感が強くなってしまい、月曜日は特に気が滅入る」と描写してもらえれば、より詳しく考えることができます。
問題が具体的に描写されると、それだけ取り組むべきことやゴールが明確になり、変化を測定するための変数も特定しやすくなります。
この例であれば、雑用とは何か、どの程度負担なのか、それに対してどのように対応しているのか、これからはどのような対応ができそうなのかということから、取り組むべきことやゴールを設定しやすくなります。
雑用はどのくらいの頻度で頼まれるのか、どのタイミングで頼まれることが多いのかということを測定して、現状把握をするポイントも見えてきます。そして、それが減ることをゴールにすれば、どの程度変化しているのかも見えてくるかもしれません。
変化の理論
多くのクライエントさんは、「自分なりに原因は何で、どうすれば解決するか」という理論を持っているものです。これを「変化の理論」といいます。この変化の理論を参考にしながらクライエントさんの話を膨らませて、問題を解決させる可能性や方法をさぐることもできます。
先ほどの例では次のように展開していきました。
雑用を押し付けられるのは確かに嫌なのだけれども、問題の核心はそこではないとクライエントさんは言い始めました。
そして、問題の本質は、自分の能力をもっと高められるような仕事をしたいことにある、ということが明らかになっていきました。
うすうす気づいていたことがカウンセラーと話すことで明確になっていったのです。
理想的なアセスメント
つまり、最初に語られた問題は、「キャリアアップへのチャレンジ意欲が膨らんできていて、まさにそのことを真剣に考える時が来ている」とアセスメントできそうです。これが心理職が行うアセスメントです。
もちろん、このアセスメントはクライエントとの協働のもと、クライエントも納得できるものでなければなりません。そして、処方(action plan)にもつながっていることが望ましいのです。
行動処方
アセスメントをこのようにしたならば、行動処方は次のように考えられます。たとえば
「まずは転職サイトを調べて1週間以内に登録してみる」、「気になっていた資格試験を調べて勉強を始める」
というものです。
もちろん、処方されるものは、小さくて実現可能があり、セッションで語られた文脈に即している方がクライエントは受け入れやすいでしょう。
それはクライエントさんの変化への動機づけを高めて、カウンセラーへの信頼も高まります。そして、行動変容につながりやすいのです。
このようにアセスメントが行動処方に無理なくつながっていくと、クライエントさんの満足度は高まります。